ヤーコン茶という名前を聞いたことはありますか?
ほんのり甘く、クセが少ないハーブティーとして親しまれるこのお茶、実は「血糖値が気になる人」からも密かに注目を集めています。
特に注目されているのが、ヤーコンの“肝臓での働き”に関する研究です。
今回ご紹介するのは、福島県立医科大学・佐藤博亮教授らによって行われた論文「Yacon diet improves hepatic insulin resistance via reducing Trb3 expression in Zucker fa/fa rats」(Nutrition & Diabetes, 2013)に基づく知見。
この研究は、ヤーコンの新しい可能性を示しているとして、国内外で高く評価されています。

インスリン抵抗性って何?
まずこの論文のキーワード、「インスリン抵抗性」について簡単に説明します。
インスリンは、食後に血糖値を下げる役割をもつホルモンです。
ところが加齢や生活習慣の影響で、「効きにくくなる=抵抗性が高まる」状態になると、血糖値が下がりにくくなってしまいます。
これが“インスリン抵抗性”です。放っておくと将来的に糖尿病などへつながる可能性もあるため、早めにケアしたい体の変化のひとつとされています。
ヤーコンに注目した、佐藤 博亮教授の実験とは?
佐藤氏らの研究では、「Zucker(ズッカー)ラット」というインスリン抵抗性を持つ実験動物に注目。
このラットにヤーコンを5週間与えたところ、いくつかの明らかな変化が見られました。

主な変化
- 空腹時の血糖値が約9%低下
- インスリンが働きやすくなる兆候(HOMA-IR)が改善
- 特に肝臓での“糖の出しすぎ”が抑えられた
体重は変わらなかったのに、これだけの変化が見られたという点に研究チームは注目しました。
ポイントは“TRB3”というたんぱく質

研究ではさらに、「TRB3(トリブルス3)」というたんぱく質にも注目しています。
これは、インスリンの信号をブロックしてしまう働きがあり、インスリン抵抗性の原因のひとつと考えられています。
ところがヤーコンを食べたラットでは、このTRB3の量がおよそ43%も減少していたのです。
さらに、インスリンの信号を受け取る“Akt”という酵素の働きも強まっており、
ヤーコンが「肝臓の糖コントロール」に良い影響を与えている可能性が示唆されました。
ヤーコン茶なら、毎日手軽に取り入れられる
この研究で使われたのはヤーコンの粉末ですが、私たちが日常的に取り入れるなら、ヤーコン茶がおすすめです。
- ノンカフェインでやさしい味わい
- 甘さはあるけど、糖質としては吸収されにくい「フラクトオリゴ糖」が主成分
- 毎日の食後や就寝前のリラックスタイムにも◎
無理なく、自然に、ちょっとだけ体をいたわる時間をつくれそうですね。
まとめ|ヤーコンは“続けられる健康習慣”のひとつかも
佐藤博亮氏の研究は、まだ動物実験の段階ではあるものの、ヤーコンが「体の内側のバランスを整える」素材として注目される理由をしっかりと示しています。
もちろん、ヤーコン茶だけですべてが解決するわけではありません。
でも、「食べる・飲む」という行為は、毎日できる小さな習慣。
自分の体と向き合いながら、安心して続けられる“選択肢”のひとつとして、ヤーコン茶を取り入れてみてはいかがでしょうか?
※ヤーコン茶を選ぶ際のポイント
ひとくちにヤーコン茶といっても、実は「葉と茎のみで作られたもの」と「芋(根)の部分も含まれているもの」の2種類があります。
それぞれに含まれる成分や風味、研究で注目されている成分の比率が異なるため、目的に合わせて選ぶことも大切です。
例えば、フラクトオリゴ糖を多く含むのは芋の部分、一方でポリフェノールや抗酸化成分に注目するなら葉の部分が使われたものに注目してみると良いでしょう。
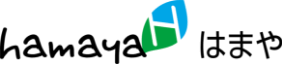

 悪質な偽サイト・詐欺サイトには
悪質な偽サイト・詐欺サイトには